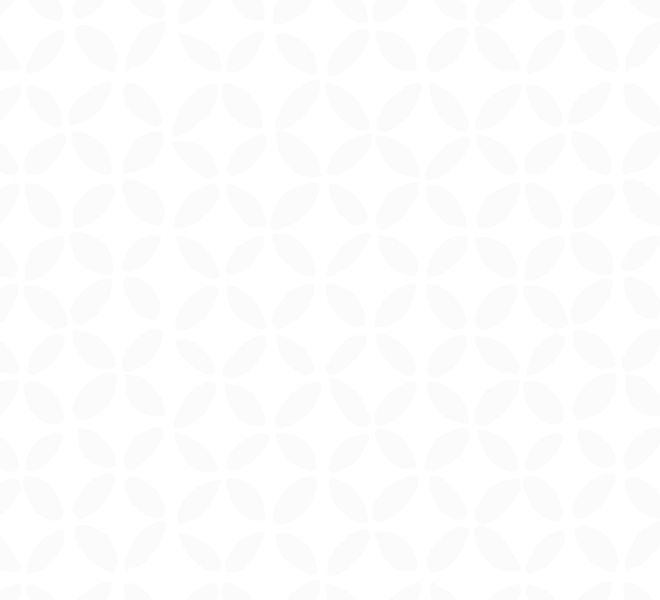みなさんは衣紋道(えもんどう)という言葉を聞いたことがありますか。着物に精通している人なら知っているかもしれませんが、そうでないとなかなか聞きなれないワードかもしれません。衣紋道とは、簡単にいうと「十二単(じゅうにひとえ)」などの装束を着付ける方法のこと。およそ900年もの長い間受け継がれてきた、日本独自の伝統技術です。今回はこの雅で美しい衣紋道について解説していきます。

衣紋道の歴史
日常生活を送る中で衣紋道(えもんどう)に触れる機会はあまりないかもしれませんが、今から3年ほど前、わたしたちの多くにその麗しい世界を垣間見る機会が訪れました。それが2019年5月1日、新しい天皇陛下が御即位となり、「平成」から「令和」へ改元された時。そして同年10月22日に行われた「即位礼正殿(せいでん)の儀」など即位に伴う一連の儀式です。陛下は天皇のみがまとうことを許された「黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)という束帯(そくたい)姿、皇后さまは「十二単(じゅうにひとえ)」姿で、唐衣(からぎぬ)や五衣(いつつぎぬ)、裳(も)を身に着けていました。その他の皇族方も束帯と十二単という装いで、平安絵巻さながらの光景が描き出されました。雅な様子をテレビで観て、惚れ惚れした人も多いのではないでしょうか。
この大切な儀式のために、念入りに準備や稽古を続けてきたのが、衣紋道の家元や旧華族の男性当主らでつくる一般社団法人「霞(かすみ)会館」の衣紋道研究会でした。装束を美しく着付けるための技術や知識を守り伝え、代替わりなどの重要な儀式で皇族の方々の着装を担当している人々です。日本の歴史を支えてきた衣紋道が、どのようにして誕生し、継承されてきたのか、その歴史を紐解いていきましょう。

衣紋道のはじまり
衣紋道(えもんどう)の起源は平安時代。本来、装束も衣服なので自分で簡単に着ることができました。実際に平安中期の貴族たちは、浄土思想の影響から曲線美を好み、装束もゆったりとしたフォルムが普通だったそう。この装束を「柔装束(なえしょうぞく)」と呼び、自分自身で着装していたと考えられています。しかし平安末期、かっちりとした格好を好んだ鳥羽上皇の影響により、装束の仕立てが大きく変化。
生地を厚くし、糊をきかせた装束が主流となりました。さらに後三条天皇の孫で、「花園の左大臣」と称された源有仁(ありひと)公と共に、威儀正しい「強装束(こわしょうぞく)」が考案されました。いわゆる男性の束帯(そくたい)や、女性の十二単(じゅうにひとえ)の現存するスタイルに近いものです。このように生地がゴワゴワとしてサイズも大きい装束は自分で着るのが難しく、人の手を借りた新しい着付けの技術が求められました。そこで登場したのが、専門的な着装技術者「衣紋者(えもんじゃ)」です。彼らの着付けの技術や考え方は「衣紋道」と呼ばれ、いまも2つの流派に分かれて伝えられています。
衣紋道の2大流派、山科家と高倉家
「衣紋道の祖」である源有仁(ありひと)公が亡きあと、独自の着装法は藤原北家の流れである徳大寺家(とくだいじけ)と大炊御門家(おおいのみかどけ)に継承されました。さらに治承4(1180)年ごろには徳大寺家から山科家へ、生安2(1300)年ごろには大炊御門家から高倉家へそれぞれ衣紋道が受け継がれ、天皇のお服上げの奉仕をしてきました。その後、明治16(1883)年には両家に衣紋教授の命が下り、いまに至るまで伝統を守り続けています。ここでは2つの家が刻んできた歴史や、着付けの違いなどを見ていきましょう。
山科家
源有仁(ありひと)公から徳大寺家(とくだいじけ)の実能(さねよし)に継承された衣紋道は、その子である公親(きみちか)へ伝えられました。さらに公親の猶子(ゆうし)となった実教(さねのり)が後に山科家の祖となったことで、徳大寺家の衣紋道は山科家に代々受け継がれることになります。室町時代に差し掛かると、初代・内蔵頭(くらのかみ)を務めていた山科教言(のりとき)に御服調達の宣旨があり、天皇・皇后両陛下、臣下たちの装束の調進と着装を担うことに。以来、歴代天皇の側近として仕え、江戸時代には公卿や堂上(どうしょう)の着装も担当しました。山科流は御服の調達から始まったこともあって、晴れの装束にふさわしい「見た目の美しさ」に定評があります。やや動きにくく崩れやすい傾向にあるともいわれますが、華麗で優美な様は見事です。加えて、山科家には歴代の当主による日記が数多く残されており、中でも13代言継(ときつぐ)の「言継卿記(ときつぐきょうき)」は、戦国時代を知るための史料として高く評価されています。現代における山科家の代表的な仕事といえば、3年前の「令和 即位の儀」が記憶に新しいところ。この時の天皇陛下ならびに皇嗣・秋篠宮殿下の着装は山科流でした。また、お雛様にも山科流の着付けが再現されているものがあります。お殿様の袖のヒダが2つ、首元に「十形」の白い綴糸があるものが山科流です。
高倉家
源有仁(ありひと)公から大炊御門家(おおいのみかどけ)の経宗(つねすけ)に伝えられた衣紋道は、その八世の孫に当たる冬信(ふゆのぶ)に継承されました。しかし冬信から継ぐ者がいなかったため、衣紋の技は助手をしていた高倉家第18代永季(ながすえ)に渡ります。第19代永行(ながゆき)は衣紋道の研究に非常に熱心で、記録書冊の整理などに励み、「装束雑事抄(ぞうじしょう)」を執筆。「中興の祖」と称されています。その他の当主たちも、「高倉家口伝秘抄(くでんひしょう)」「撰塵装束抄(せんじんしょうぞくしょう)」「装束着用次第」など多くの本を著し、衣紋道の心得を後世に残しています。高倉家は後に御服調進にも関与しますが、着装を以って始まったため、身にまとうための衣紋道に重きを置いているのが特徴的。控えめで簡素、その分動きやすく実働的な着付けだといわれています。江戸時代には、院・将・武家の着装は高倉家が担当していたそうです。現在は「高倉流・有職文化研究所」を主宰し、「令和 即位の儀」では、天皇陛下と秋篠宮殿下以外の男性皇族の着装を担当しました。お雛様はどちらかというと高倉流で着付けられているものが多め。お殿様の袖のヒダが1つ、首元の白い綴糸が「×形」になっていれば高倉流です。我が家のお雛様は山科流と高倉流どちらなのか、見比べてみるのも面白いでしょう。
装束の種類について
装束と一言でいっても、種類は実にさまざま。儀式によって着用できる装束もいろいろです。この章では代表的な装束を男女別にご紹介します。

男性の装束 天皇陛下
・黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)
ありとあらゆる皇室祭儀において、天皇陛下が最も多く用いられる束帯の一種。天子のみが召される御服。黄櫨(こうろ)で染めた生地に、桐や竹、鳳凰(ほうおう)、麒麟(きりん)の地紋が表されています。宮中三殿の恒例祭祀の大祭および小祭をはじめ、御成年式、大婚式、立太子式などに用いられます。大礼の場合、三殿に期日奉告の儀、即位後大一日賢所御神楽の儀(かしこどころみかぐらのぎ)、即位礼、大嘗祭(だいじょうさい)後神宮に親謁の儀(しんえつのぎ)、ことに即位礼当日紫宸殿の儀(ししんでんのぎ)にも召されます。3年前の「令和 即位の儀」でも着用されていました。
・御祭服(ごさいふく)
なによりも清浄で神聖な御服として、御神事の際に召されます。純白生織りの絹地を使用。御一代一度の大嘗祭の場合、悠紀・主基両殿の儀式に用いられ、祭祀の中でも一番重大な新嘗祭(にいなめさい)の時にだけ召されます。頭にかぶる御幘(おんさく)の御冠は、山科流は後ろ側で諸鉤結び(もろかぎむすび)に、高倉流は左側で片鉤結び(かたかぎむすび)にします。
・帛御服(はくのごほう)
御祭服に次ぐ御服。純白の帛(絹)で作られています。大礼の際、即位礼の当日賢所大前の儀や頓宮(とんぐう)より廻立殿(かいりゅうでん)に御渡の時に用いられます。年中恒例の祭儀に用いられることはありません。
・御引直衣(おひきのうし)
御直衣(おのうし)の裾を引いて歩くことからこの名が付いたといわれています。大礼の場合、神宮、神武天皇の山陵、前帝四代の山陵に対する勅使発遣の儀(ちょくしはっけんのぎ)のみで使用。下に紅の長袴を履きます。
・御直衣(おのうし)
大礼以外に臨時で行われる神宮、山陵への勅使発遣の儀、大嘗祭前2日の御禊(ぎょっけい)、神武天皇祭および先帝祭の当夕方に行われる御神楽の儀、毎月1日の旬祭(1月1日は除く)御親拝(ごしんぱい)などでお召しになります。
・御小直衣(おこのうし)
御直衣よりもさらに略式の御服なため、御即位礼などには用いません。毎年6月と12月の節折(よおり)のほか、宮中より神宮および神社に御奉納になる御霊代(みたましろ)御覧、大喪(たいそう)後に行われる一周年祭の翌日の御禊の儀などでお召しになります。
女性の装束 十二単(じゅうにひとえ)
十二単(じゅうにひとえ)は宮中における成人女性の第1正装です。平安時代中期に完成し、宮中などの公の場で晴れの装いとして用いられてきました。現在では主に、御即位の大礼の儀や皇族妃の御成婚の儀で召されています。十二単はさまざまな衣を重ねて着る非常に複雑な装束です。どのような構成になっているのか解説します。

・唐衣(からぎぬ)
唐衣(からぎぬ)は十二単の一番上に着る衣です。そのため最も美しくデザインされています。名前の通り唐服を模したもので、上半身までの短い着丈になっているのも特徴。地位によって色目や文様、地質に区別がありますが、一般的には地文の上にさらに別の色糸で上文を織りだした二重織物が用いられています。裏地には板引きの綾絹などが使用され、非常に贅沢な作りです。
・表着(うえのきぬ・うはぎ)
唐衣の1枚下に着る衣のこと。もう2枚下に着る五衣(いつつぎぬ)の襲(かさね)が見えるように少し小さめに作られています。「内に着る衣」を語源とする袿(うちき)の中で一番上に着る衣なので、この名が付いたのだそう。生地には二重織物などの高級品が用いられ、裏は無地、袖や衿、裾は1cmほどお退り(おめり)に仕立てられています。色は赤や萌黄、二藍、重色目が多め。文様は立桶、唐草、菱文などが主流です。
・打衣(うちぎぬ)
表着(うえのきぬ・うはぎ)の1枚下に着る衣で袿の一種。紅染めの衣。紅の綾を砧(きぬた)で打って艶を出していたことが、名前の語源になったといわれています。後に打つ代わりに、布地に糊を付けて漆塗りの板に張り、よく乾かしてから板から引きはがすという手法で光沢を出すようになりました。色は紅色または濃色(こきいろ)。表地には綾を、裏地には平絹を用います。
・五衣(いつつぎぬ)
5枚重ねて着る袿のことを五衣(いつつぎぬ)と呼びます。鎌倉時代以降に5枚で定着しましたが、平安時代には20枚重ねていたという記録が残っています。袷仕立てで、袖口、衿、裾が細く見えるようにさしはさんで着用します。表地には有識文様を織りだした唐綾や綾、裏地には平絹を使用。文様は地文のみ。5枚の色の取り合わせや重ね方を重視しており、これを襲色目(かさねのいろめ)といいます。
・単衣(ひとえ)
袿のさらに下に着る肌着のようなもの。形自体は袿と同じですが、丈と桁がやや大きく長く仕立てられています。色に決まりはない一方で、文様は菱に限られています。地質は絹や綾など。単と書くことも。
・長袴(ながばかま)
前の開きを覆うために履きます。袴といっても形は筒状で、長い裾を後ろに引くのがポイント。糊を利かせた張袴(はりばかま)と、砧打・板引きして作られる打袴(うちばかま)があります。現在は経糸(たていと)よりも緯糸(よこいと)を太くして横に強い張りをもたせた精好(せいごう)という絹織物を用いるのが一般的です。
・裳(も)
元々は巻きスカートのようなものでしたが、平安時代に多くの衣を重ね着するようになって腰に巻きつけることができなくなったため、それ以降は腰に当てて結び、後ろに垂れて引くようになりました。色は白、赤、青、裾濃(すそご)など。地質は経(たて)生絹、緯(ぬき)半練りの綾織物。夏は穀織(こめおり)や紗になることも。松や鶴、鳳凰などの模様が施されています。
まとめ
いかがでしたか。日本の装束は長きに渡って受け継がれてきた、世界でも他に類を見ない特別な衣服です。雅で美しい出で立ちの裏側には、常に衣紋道(えもんどう)の存在がありました。私たち1人1人が衣紋道の存在を知ることで、きっと日本の宝である伝統文化を後世に残すための一助となるはずです。



 振袖
振袖 0532-47-1101
0532-47-1101
 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム